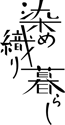【清野詳子(みつこ)さんプロフィール】
1978年、女子美術短期大学造形科卒業後、実家である清野工房主宰 清野新之助に師事。
現在は、清野工房染織教室にて指導にあたり個人としてはグループ展に向けて、制作している。
【清野工房ホームぺージ】https://seinokoubou.net/
【オンラインストア】https://shop.seinokoubou.net
【 Instagram 】@gonbennihitsuzi
たくさんのお弟子さんをかかええ、制作工房として活動してい清野工房は、父・新之助さん、母・恭子さん、詳子さんの3人での運営へと移行します。その頃のことをお聞かせいただけますか。
―清野さん
私は出産・子育て中 2年間は糸を紡ぐことだけしていましたが、子供が保育園に入った頃から自転車で工房に通い始めました。
その後、30歳の頃に清野工房は父、母、私の3人体制での運営となりました。
最初の弟子入り時代は、父や母のデザインを弟子達が作るという制作でした。3人体制になった頃から、ようやく「こういうものを作ってみたいな」と思うようになりました。
使ってもいいと言われた残糸でミニマフラーなどを作ることからはじめました。最初の頃は、色を基準に作ってチクチクする糸もおかまいなしで使っていました。
失敗もたくさんして、次第に現在につながる作品づくりの指標が出来てきたように思います。
しばらくして、「清野工房 服地織り講座」という3カ月間の織物教室を始めました。年に2回の開催から始まり、その後月4回の週一教室も始めました。
私たちが思っていた以上にたくさんの方がホームスパンの織物を学びたいと言って通って来てくださいました。
父と母は教室で生徒さんの指導をし、展示会に向けては父母の指示のもと、私は父が試作した織物やフェルトのサンプルをもとに清野工房の作品の制作をするという役割分担でした。
当時から展示会の準備のアイロンがけ、タグ付け、梱包は私がやっていましたから、もう何十年とくり返しているわけですが、何回しても慣れない作業です。
父が81歳の時にカード掛けする大型機械で手に大きな怪我を負ってしまいました。教室の指導は私が担当することになりました。突然のことでしたが、父は教室指導は退いたとはいえ、工房内にいましたので心強かったです。
詳子さんの作品づくりといえば「手紡ぎ」がキーワードであるように思います。
どのような視点で作品作りに取り組んでおられるのでしょうか。
―清野さん
糸を紡ぐことは好きです。
木綿、カシミヤ、キャメルなどの繊維が短いものを紡ぐのにはチャルカを使います。
回転比が大きいから、紡毛機より効率良く紡げます。
父はウールだけではなく、絹で制作する仕事をたくさんしていた頃もありましたが、私は異素材を混毛したり、手紡ぎしたウールや綿を組み合わせ織ることに興味があります。
羊の種類によって、制作の過程で毛に起こる変化が違なるところも面白いと思っています。
私は単糸の動きがおもしろくて、単糸で織ことが多いです。撚りの強さや織るときの間隔の違いで表情や糸の動きがそれぞれ単糸であることでより引き出せると思います。
織りの工程では、複雑な組織織りはせず、4枚綜絖をベースに平織りや綾織りのシンプルな織りで、単糸の糸と糸がどのような表情を生み出すのかを楽しんでいます。
オーダー品ではないものを作る時は、自分が欲しいものというのが糸口になったり、素材の特性によって何を作るのに適しているのか、というとこからイメージしたりします。身につけて使えるものをつくりたいと思っています。
展示会で売れる、売れないは、作品と見る方のフィーリングや出会い、そういうところによるかなと思います。
父も、買ってくださるということが対価だと言っていました。
作品制作では思う通りにいかないこともあるのでしょうか。
―清野さん
仕上げの過程で、この羊毛の場合はかなり縮絨しないと良さが出てこないんだ、とか平織より綾織が向いている羊種だなとか気づかされます。失敗によって発見を繰り返して制作しています。
失敗という体験で織り作業で起こる様々なトラブルにも対処できる想像力が養われたのかもしれません。
また、私が試した羊種や織りの情報が、教室の生徒さん達の織りたいもののテーマになっていくこともあるようでそれも嬉しいです。
清野さんご自身にとって、作品作りとはどのような位置付けなのでしょうか。
また、これからやっていたいことはありますか。
―清野さん
教室の仕事があるので、常に自分の新しい作品作りを意識しなければいけないのは大変なのですが、清野工房はずっと作品を作って販売する工房でしたので、常に「作る」ということが自分の体に染み付いてしまっている感じなんだと思います。

―清野さん
糸を紡ぐことは仕事をしているという感覚ではないように思います。
それから最近思うことは、これまでの展示会では「作品づくり」の背景の説明が足りていなかったと気づきました。羊毛と紡毛機を置いてタグには羊種を書いておく、そのくらいしかしていなかったです。
展示会で「紡いだ糸じゃないのね」と言って展示を見るのをやめてすぐに会場を出ていってしまう方がおられました。その方にとっての「紡いだ糸の織物」のイメージとは違っていたのかもしれません。
また、タグに羊種「チェビオット」と書いていても、紡ぎや織りをしない方にとってはそれだけでは何の情報にもなりませんでした。
展示会に来てくださる方は紡ぎや織りを知っている人が多いので、詳細な説明は必要なかったのかもしれないのですが、ホームスパンがどのような工程で、どのように人の手で作られているのか、ということを説明する努力、知っていただく努力をすることが必要だと、今改めて思っています。
いろんな羊種がいて、羊毛もいろいろある中、私たちはこんなことを思いながら、一本のマフラーを作っていますということをお伝えしてみたなと思いはじめました。
弟子として働いている頃は、自分のオリジナルの制作に夢中になるような余裕や欲もなかったですが
今は、羊毛との出会いもあり、自分の心の赴くままに、導かれるままに制作しています。
<終わり>
***
清野詳子さん/清野工房の2025年の活動予定:スピニングパーティ2025へ出展予定。
詳細は清野工房のホームページ、Instagramなどからご確認ください。
[取材・撮影 ] 遠藤ちえ / 遠藤写真事務所